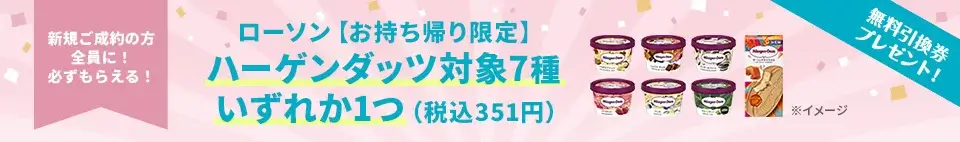自動車保険は任意保険であり、加入が義務付けられているものではありません。また、生命保険のように、満期時に満期返戻金が戻ってくるものではありません。1年の中で無事故を達成すると等級は1つアップしますが、ほとんどの保険会社は20等級を限度にそれ以上の等級アップはできません。
では、自動車保険は無事故の場合には本当に無駄な保険なのでしょうか。任意保険であり、自賠責保険のように強制されないのであれば、未加入でも良いのでしょうか。そこで、この記事では「自動車保険の加入の意義と未加入の注意点」についてクローズアップします。ぜひご一読ください。
この記事でわかること
- 自動車保険が無事故なら無駄になるのかどうか
- 自動車保険に加入する意義
- 無事故でも実は損をしない理由
- 自動車保険未加入時の注意点
- セーフティードライブのコツ
無事故であっても自動車保険は必要か
自動車保険は事故の際に大きく分けて2つの補償を実施しています。1つは相手方への補償、そしてもう1つは自分への補償です。
事故が起きると、事故の相手方にケガや車両の損壊などのダメージを与える可能性があり、補償を用意する必要があります。自動車保険は相手方への補償を用意しており、重い「賠償責任」をカバーしてくれます。
一方で、加入者自身の補償についても用意しています。自身の契約車両やケガについても手厚く補償してくれるのです。自動車保険は掛け捨てのため、無事故の年度が続いていると不要に感じるかもしれませんが、いつどこで、事故が起きるかはわかりません。無事故が続いていても、自動車保険への加入は必要です。
自動車保険の必要性と加入の意義
自動車保険はなぜ必要とされるのでしょうか。「自賠責保険があるから、任意保険は不要」と感じていませんか。
しかし、自動車保険は自賠責保険とは比較できない範囲の補償を用意しており、被害者・加害者の双方を守るだけではなく、家族も含めて守っている保険なのです。
自動車保険の必要性は、以下の2点です。
1.自賠責保険では圧倒的に補償が足りない!
自賠責保険は「強制保険」と言われており、自動車やバイクを運転する方なら強制的に加入する必要があります。しかし、自賠責保険の本質は「被害者救済」にあるため、事故を起こしてしまった加害者側の補償は用意されていません。自賠責保険はあくまでも「被害者の死亡とケガ」を補償するものであり、事故によって発生するほとんどの賠償責任をカバーしていないのです。
| 物への補償 | 人への補償 | |
|---|---|---|
| 自賠責保険(強制保険) | × | △(対人賠償のみ、限度額あり) |
| 自動車保険(任意保険) | 〇 | 〇 |
対人賠償部分にしか補償が無い強制保険では、その他に必要な補償が得られません。自動車保険の加入意義とは、自分の身体や車両はもちろん、家族の生活を守るためと言えるでしょう。
2.高額の賠償責任に備えが無い!
自賠責保険があるにもかかわらず、多くの方が任意保険である自動車保険に加入している背景には、事故による被害には「高額の賠償責任」がともなうことも挙げられます。
たとえば、自動車事故によって被害者側に頸髄損傷などの重い障がいが残された場合、訴訟の結果加害者側に億単位の支払いが命じられることがあります。任意保険に加入していると、こうした重い賠償責任にも備えられます。
無事故でも次年度の契約に特典はない?
自動車保険は基本的に1年契約となっており、始期日から満期日までの1年間を補償します。では、事故が無ければ(もしくは事故による保険金支払いが無ければ)翌年の契約に特典は用意されているのでしょうか。
1等級アップする
無事故や等級に影響する事故は無かった場合、翌年度の自動車保険の契約は1等級アップします。等級が上がっていくことで基本的には保険料が安くなるため、お得になります。
【等級】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
自動車保険の等級制度とは?保険料の割増引率を徹底解説
無事故割引がある
前年度の保険契約期間中に無事故だった場合には、「無事故割引」が用意されます。無事故割引とは、前契約の保険会社がどこであっても適用されることが多く、中断証明書の利用でも適用を認める保険会社がほとんどです。たとえば、有名なダイレクト損保は一定の条件を満たすと、保険料を2,000円割引する無事故割引を導入しています。
このように、事故が無かった場合には、等級アップや無事故割引と呼ばれる特典が用意されています。生命保険のように満期保険金は無くても、翌年の保険料に還元されるしくみはあることを知っておきましょう。
無事故だからこそ検討すべき補償のポイント
自動車保険は等級のみで保険料が変動するのではありません。ご自身の求める補償範囲や、運転される方の年齢、所有している車両によっても変動します。
一般的に事故が無ければ翌年の自動車保険料は下がる傾向がありますが、補償などを見直すことで保険料が上がることも考えられます。では、本年度無事故だった場合には、どのような視点から、翌年の保険料を検討するべきでしょうか。この章では、補償の視点から保険契約を見直すポイントを紹介します。
前年同条件でも保険料が上がる理由
無事故の場合、等級アップと無事故割引があるため、保険料が下がる傾向があります。しかし、前年同条件で保険契約をしようとしても、「保険料が上がってしまった」というケースも少なくありません。では、どうして前年同強権でも保険料が上がるのでしょうか。
1.走行距離の増加
自動車保険は走行距離が多ければ多いほど、運転する機会が多いため「事故発生リスクが高い」と考えます。そのため、走行距離が前年度よりも多くなると、走行距離区分が見直しされてしまい、保険料が上がってしまうことがあります。
2.年齢条件の変更が起きた
前年度同条件でも、被保険者の年齢が高齢化していると、自動車保険料が高くなることがあります。
3.型式別料率クラスの変更
型式別料率クラスとは車両の型式ごとにリスクの大きさを数値で表したものです。この料率クラスは毎年改定が行われており、前年度の事故の有無に左右されることなく、保険料に大きく影響を与えます。もしも契約している車両の料率が改定された場合、保険料が上がってしまうことがあります。(一方で、下がることもあります。)
【型式別料率クラス】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
型式別料率クラスで保険料が変わる仕組みとは?
4.保険全体の改定
自動車保険は各保険会社が販売しており、時々補償内容や保険料の見直しも行っています。前年度と同条件の保険契約であっても、保険会社側の見直しによって保険料が上がることがあります。
補償を見直すメリット・デメリット
自動車保険の保険料は、無事故だった翌年であっても上がってしまうことがあります。そこで、自動車保険の保険料を抑える場合には、「補償を見直す」という方法があります。
しかし、自動車保険は自賠責保険ではカバーできない部分を補っている保険です。高額の賠償責任に備え、自身への補償も用意するためには、しっかりと補償を用意しておくことがおすすめです。
では、保険料節約を目的に補償を見直す場合には、どのようなメリット・デメリットがあるでしょうか。
- 【メリット】
- 補償を見直すことで、不必要な補償をカットできる
- 必要な補償が現契約にない場合、他社への切り替えも検討できる
- 家族と重複している補償を毎年確認し、保険料の過払いを防げる
- 【デメリット】
- 必要以上に補償を削ってしまい、実際の事故の際の補償が得られない
- 誤って補償を削減すると、対象とならない運転者が発生するおそれがある
補償を見直すことは重要ですが、見直しを保険料目的に進めてしまうと、補償が減りすぎたり、誤って本当は必要な補償を見落としてしまったりするおそれがあります。見直す際には、「自動車保険は事故時に必要な補償を網羅している保険」であることをしっかりと覚えておきましょう。
無事故時に補償を見直す|知っておきたい3つのポイント
無事故が続いている方は、自動車事故のリスクや危険性の実感がなかなか生まれず、思いきって補償を減らして保険料を節約することを検討するかもしれません。しかし、無事故であっても翌年には事故に巻き込まれるおそれは否定できません。
運転をする以上は、加害者・被害者のいずれの視点からも補償に備えておくことが重要です。では、無事故時に補償を見直すなら、どのようなポイントを押さえておくと良いでしょうか。以下3つのポイントをご確認ください。
1.無事故が続く方におすすめの保険料節約術
自動車保険のご加入後に継続して無事故が続いている方は、優良ドライバーの証拠です。そんな方におすすめの保険料節約術は、「車両保険の見直し」です。車両保険は契約している車両を守るために大切な保険ですが、車両の修理・全損に備えるために保険料が高く設定されていることがあります。そこで、以下の方法を検討してみましょう。
【免責金額の見直し】
車両保険の免責金額を高く設定しておくと、万が一の際にはその免責金額は契約者側が負担する分、保険料は安くなります。
【参考例】
車両保険金額100万、免責金額5万円の場合
→全損時には95万円が保険会社、5万円は自己負担となる
5万円を負担しなくて良い保険会社は、自動車保険料を予め安くしています。
無事故なら無駄に感じる自動車保険であっても、免責金額を設定すれば、車両保険の補償は残しつつ、保険料の節約ができます。
【車両保険金額の見直し】
本来は自動車保険を販売する保険会社側は、車両保険におすすめの金額を、毎年の契約時に算出して見積もりしています。車両保険は自由に契約者が保険金額を決めるのではなく、「自動車保険車両標準価格表(単価表)」を使って算出されます。
中古車や初度登録から経過している車両は、自動的に減価償却され、ほぼ価値が無く車両保険の金額も少額しか入れないことが多いでしょう。(実際の市場価値とは異なる)
この場合、大きな損害に備える保険金額が元々設定できないため、思いきって補償を減らすことも選択肢の1つです。
2.等級の割引率を知っておく
自動車保険にはノンフリート契約とフリート契約があり、一般の方が加入しているノンフリート契約には等級制度が導入されています。等級は高ければ高いほど、「割引率」が高くなるため保険料は安くなります。
ここで、等級による割引のしくみをおさらいしておきましょう。
- ノンフリート等級について、ほとんどの保険会社は「1~20等級」で表しており、数字が大きいほど割引率は高い
- 事故があれば翌年の契約時に3等級ダウン、無事故なら1等級アップする。1等級ダウン、等級据え置き事故と呼ばれるものもある。
- 1度事故を起こすと、「事故有係数期間」が適用されるため、無事故期間であっても一定期間保険料の割引率が下がる
等級は前年度に事故が無ければ1等級ずつ上がりますが、「事故有係数期間」の間は割引率が低い状態で続きます。
【参考例:等級別割増引率例 10等級と11等級の場合】
| 10等級 | 11等級 | |
|---|---|---|
| 無事故 | -46% | -48% |
| 有事故 | -19% | -20% |
事故有になると、同じ10等級や11等級であっても、割引率が大きく異なっていることが分かります。
事故が起きるとこのように保険料に影響するため、注意が必要です。
補償を見直しても思うように保険料が下がらない場合は、事故有係数期間が影響している可能性があります。事故有係数期間は保険会社を変えても影響は続くため、他社へと契約を変更しても保険料にあまり大きな差異はない可能性があります。
参考URL:一般財団法人 日本損害保険協会
自動車保険の「等級」について教えてください。
3.現契約の契約先の見直し
無事故の場合でも型式別料率クラスの改定などで、次年度の自動車保険の値段が上がってしまうことがあります。そこで、補償を見直すためには、現契約の契約先の見直しもセットで行いましょう。
現契約が代理店を経由している自動車保険の場合、スマホやパソコンで自身が手続きをして加入するダイレクト型損保(ネット型損保)なら欲しい補償はそのままに、保険料が安くなる可能性があります。
【保険の見直し】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
自動車保険見直しはいつ?知らないと損するタイミング!
自動車保険は無事故なら無駄?未加入時の注意点とは
自動車保険は無事故の状態で何年も契約していても、所有している車両や運転者の年齢条件などの影響により、必ずしも年々保険料が安くなってくれるものではありません。では、自動車保険は無事故なら無駄なのでしょうか。
この章では、未加入時の注意点について中心に詳しく解説を行います。
示談交渉を自分で行う必要がある
自動車保険にはサービスの1つとして、「示談交渉サービス」が提供されています。
示談交渉サービスとは、事故時に保険会社側が加害者・被害者側と示談交渉を行ってくれるサービスです。一般的には、事故時には相手方も自動車保険に加入している場合は、保険会社間で示談交渉を成立させます。また、歩行者や自転車の乗車中の方への示談交渉や、電柱や民家への損害の場合は、その持ち主への示談交渉も行います。
自動車保険に加入していない状態で、もしも事故を起こしてしまったら、相手方との示談交渉はご自身が行う必要があります。
示談交渉は、相手方との過失割合を決めるだけではなく、賠償金額の交渉なども行う必要があります。自動車保険に未加入の状態で、法的知識も必要な難解な交渉をご自身で行うことは事実上困難でしょう。
賠償責任に備えがない
事故が起きてしまい相手方に損害を与えてしまったら、補償を支払う必要があります。死亡やケガに関しては一定額が自賠責保険から支払われますが、物損部分に対しては自賠責保険では支払われないため、ご自身で支払う必要があります。
先に触れたように自動車保険に未加入の場合は示談交渉も自分で行う必要があり、不利な状況に陥る可能性が高いでしょう。
死亡事故、高度な後遺障害が残る事故の加害者となった場合、自賠責保険だけでは補償が補えないため、訴訟となる可能性もあります。賠償責任に備えるためにも、任意保険は必須です。
ご自身の補償がなく、生活が困難になる
自動車保険が必要とされる方は、自動車を所有しており使用目的がある方です。通勤や通学、業務目的、レジャーであれ、定期的な頻度で自動車に乗る必要があります。もしも自動車が事故によって全損、自身もケガをしてしまったら、自動車を買い替える必要があり、自身のケガについても治療を行う必要があります。
しかし、自身が被った損害については、自賠責保険ではカバーできないため、自身で支払うほかありません。自動車保険に加入しなかったために、1つの事故で家族も含めて生活が困難になってしまうおそれがあるのです。
無事故の状態を続けよう!セーフティドライブのコツとは
常に高額の補償の備えを用意してくれている自動車保険は、未加入を選択するのではなく、無事故の状態を維持できるように「安全運転を続けること」が重要です。
保険料が高いから!無事故だから!などの理由で自動車保険を解約してしまうと、補償が得られません。
そこで、この章では保険料を安く維持するためにも、「セーフティドライブのコツ」を紹介します。
ハイビームの活用
神奈川県警察では、事故が多くなりやすい夕暮れ時の運転には、「ハイビームの活用」が有効であると伝えています。
神奈川県では、令和4年に道路で横になってしまった人が交通事故に巻き込まれたケースが、18件発生しました。うち、ロービームで走行していた車両が轢いてしまい、亡くなってしまった死亡事故は9件です。
夜は事故で転倒した方、泥酔してしまった方などが、道路に倒れていることがあり、照明が少ない場所の走行は「ハイビーム」を使うことがおすすめされています。
道路交通法第52条では、対向車がいない場合は基本的にハイビーム走行をすることを定義づけています。この機会に夜間走行がある方は、運転技術の向上のためにもハイビームの活用を検討しましょう。
![]()
引用元:神奈川県警察 夕暮れ時の早目点灯・セーフティドライブ
運転履歴の記録と有効活用
近年運転履歴の記録や、その記録の有効活用に関心が高まっていることをご存じでしょうか。
トヨタが提供している「コネクテッドサービス」の場合、マイセッティングを設定することで、ドライバーの好みの設定が記録され、安全なドライブを快適に楽しむことができます。ナビやオーディオの音量設定から、運転席のシート位置も記録します。
1台の車を複数の方で運転される場合に便利なサービスでしょう。また、コネクテッドカーと呼ばれる技術も進化しています。運転履歴に関してデータが集計されており、自身の運転の傾向がわかるしくみです。このしくみを生かしたテレマティクス保険も登場しており、安全運転が保険料に直結する時代が到来しています。
ドライブレコーダーの活用
近年ドライブレコーダーへの関心も高まっています。安全運転を直接記録しているコネクテッドサービスとは異なりますが、ドライブレコーダーの活用もおすすめです。
ドライブレコーダーは事故時の記録としての役割ももちろんありますが、近年が技術の進化によって「安全運転支援機能」がプラスされつつあります。
この機能は前方との車両の距離を知らせる、速度超過について警告するなどの機能があります。車線をはみ出してしまったときに警告音を発するタイプもあるので、初心者や高齢者のドライバーに搭載することがおすすめです。また、コネクテッドカーをお持ちではない方でも、ドライブレコーダーを搭載すれば、最新技術を体験できます。
事故リスクが高いドライバーとは?
自動車保険は「無事故なら無駄」になるものではなく、無事故を続けるからこそ保険料が節約できるため、安全運転を常日頃から心がける必要があります。
では、事故のリスクが高いドライバーとは、一体どのような方でしょうか。
高齢者ドライバー
日本は現在超高齢化社会を迎えており、運転免許を保有する高齢者も増加の一途をたどっています。「運転免許統計 令和3年版」によると、2021年3月末現在で65歳以上の免許を保持する高齢者は23.5%で1927万8887人です。
また、75歳以上でも609万8474人で約7.4%にも上っており、非常に多くの高齢者が全国で運転をしていることが推測されます。運転免許証は顔写真があるため、身分証明書として重宝されることが多く、どうしても返納はできないと感じる方も多いでしょう。
しかし、高齢者は視力や体力の低下も起きやすく、認知症のリスクも若年層より高いため、高齢者ドライバーは事故リスクが高くなっています。近年は高齢者ドライバーによる事故も多く報道されており、返納に関しても家族全員で検討することがおすすめです。
参考URL:察庁交通局運転免許課
運転免許統計 令和3年版
初心者ドライバー
自動車保険料は、一般的に「全年齢条件」が一番高い保険料設定となっていますが、これは若年層の事故リスクが高いためです。運転免許証を取得できるのは満18歳以上(原付の場合満15歳以上)です。初心者運転中はまだ経験も浅く、運転ミスなども多発する傾向があります。
初心者の方は無理な追い越しなどは行わず常にセーフティドライブを心がけることが大切です。車間距離も詰め過ぎず、夜間走行時にも十分に注意しましょう。
高齢者マーク・初心者マークは表示する義務がある
運転リスクの高い高齢者や初心者には、「マーク」の貼り付けが義務付けられていることをご存じでしょうか。事故リスクを避けるためにも、以下に該当する方はしっかりとマークを貼ってください。(標識にはこの他に、聴覚障害者マークや身体障碍者マークもあります)
| 初心者マーク (初心運転者標識) | 高齢者マーク 高齢運転者標識) | |
|---|---|---|
| 表示対象者 | 普通自動車もしくは準中型自動車の 免許証を取得後、1年未満 | 普通自動車を運転できる方で 年齢が70歳以上 |
| 表示義務 | 反則金・行政処分点数1点あり | 罰則などはありません |
| 表示対象の車両 | 普通自動車 軽自動車 準中型自動車 | 普通自動車 軽自動車 |
参考URL:警視庁
自動車の運転者が表示する標識(マーク)について
まとめ
今回の記事では、「自動車保険の加入の意義と未加入の注意点」をテーマに、詳しく解説を行いました。
自動車保険は任意保険であり、加入が義務付けられているものではありませんが、ご自身や家族、事故で発生する賠償責任に備えるためにも加入は必須です。
生命保険のように、満期時に満期返戻金はありませんが、無事故が継続できていると等級はアップし、無事故割引も継続できます。安全運転を心がけながら、本記事を参考に自動車保険の加入の必要性を改めて見直してみませんか。