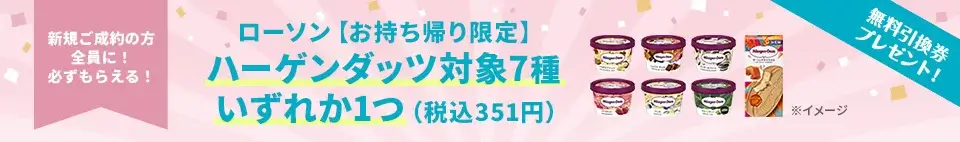任意保険である自動車保険は、保険料が車種や加入する期間によってあらかじめ決められている自賠責保険(強制保険)とは異なり、さまざまな条件によって保険料が変動します。補償内容や免許証の色など、実に多くの条件が保険料に影響しますが、その中の1つに「年齢条件」があることも知っておく必要があります。
自動車保険は運転される方の年齢によって、保険料が大きく異なるのです。そこで、この記事では自動車保険の保険料が「年齢で変わる」ことに注目します。
年齢条件のしくみについてはもちろんのこと、運転者年齢条件特約についても詳しく解説しますので、ぜひご一読ください。
この記事でわかること
- 年齢条件とはなにか
- 年齢条件を誰に設定するか
- 若年のドライバーの保険料が高い理由
- 高齢者と若年層の事故リスクの違い
- 高齢者の自損事故リスク
運転者の年齢は自動車保険料にどう影響する?
任意保険である自動車保険は、基本補償や特約の中身を任意で付帯できるため、保険料も契約者一人ひとりによって大きく異なります。では、具体的に運転者の年齢は自動車保険にどう影響するのでしょうか。
この章では年齢と保険料の関係について詳しく解説します。
運転者の年齢とは
「運転者の年齢」とは自動車保険において実際に運転される方の年齢を意味する言葉です。保険会社や共済は運転される方の年齢や車種などのリスクを分析しており、自動車保険料を決めるにあたっての判断材料としています。
「運転者の年齢」については事故リスクに深い因果関係があるため、「告知義務」として申告を求めています。保険契約者と運転される被保険者の年齢が異なる場合は、被保険者側にあわせて告知する必要があります。
運転者の年齢が低いほど自動車保険料は高い
自動車保険では、運転者の年齢が低いほど、保険料を高く設定しています。
その理由には若年層の方が事故を起こすリスクが高いことが挙げられます。普通車の運転免許証の取得は18歳以上のため、自動車の運転者の最も若い年齢は18歳です。
10代から20代の方が初めて自動車保険に加入すると、その保険料の高さに驚く人も少なくありません。しかし、通勤・通学で自動車を運転する以上は自動車保険にしっかりと加入し、事故に備えておく必要があります。
年齢条件とは
自動車保険の保険料は、年齢が1つ上がるごとに変動するのではなく、年齢条件の設定によって保険料が変動します。
年齢条件とは、以下の区分が一般的です。(保険会社や共済によって年齢条件が異なる場合あり)
なお、年齢条件は運転される方を年齢区分によって限定するもので、保険料の節約効果もあります。
- ① 全年齢条件
運転される方なら、年齢を問わずに補償します。 - ② 21歳以上限定
運転される同居のご家族などが、21歳以上の場合に補償します。21歳以上の方の補償は行わない代わりに、保険料は①よりも安くなります。 - ③ 26歳以上限定
運転される同居のご家族などが、26歳以上の場合に補償します。26歳以下の方の補償は行わない代わりに、①・②よりも保険料が安くなります。 - ④ 30歳以上限定
運転される同居のご家族などが、30歳以上の場合に補償します。30歳以下の方の補償は行わない代わりに、①~③よりも保険料が安くなります。 - ⑤ 35歳以上限定
運転される同居のご家族などが、35歳以上の場合に補償します。35歳以下の方の補償は行わない代わりに、①~④よりも保険料が安くなります。
(※ただし、実際の自動車保険の保険料は等級や補償内容によっても大きく異なります。)
年齢条件は誰に合わせる?
年齢条件は運転者の中で最も若い年齢の方に合わせる必要があります。
年齢条件は上記の通り、対象となる年齢以下の方は補償を行わないことで、保険料を節約できるしくみを採用しています。
たとえば、自宅にある自動車を、同居している18歳の子と48歳の父親の2人が運転する機会がある場合、父親の年齢条件である35歳以上に設定してしまうと、子が事故を起こした際に補償ができません。この場合は全年齢条件に設定する必要があります。
年齢条件以外でも補償されるケースもある
運転者の年齢条件に含まれる方は、あらかじめ決められています。実は、年齢条件に該当しない方は一律に補償が受けられないのではありません。
まずは年齢条件の該当者を解説します。以下の①~④の方は自動車保険の契約で設定する年齢条件に該当します。
- ① 記名被保険者(主に運転する方)
- ② 記名被保険者の配偶者
- ③ 記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族
- ④ ①~③の方に業務で従事している方 (家事は除く)
①~④にあてはまる方は、年齢条件の区分外だった場合、事故時の補償が得られません。たとえば、記名被保険者が40歳、その配偶者が25歳、年齢条件が35歳以上に設定してしまったら、配偶者は年齢条件の対象者のため、配偶者が補償対象外となってしまいます。
しかし、記名被保険者の別居している子が20歳、記名被保険者が40歳だった場合は、別居の未婚の子は①~④に該当しないため補償対象となります。年齢条件を別居の未婚の子に合わせなくて良いのです。
分かりやすく以下にまとめましょう。
| 年齢条件の対象者 | 年齢条件の対象外 (年齢条件に関係なく補償してもらえる) |
|---|---|
| ①記名被保険者(主に運転する方) ②記名被保険者の配偶者 ③記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族 ④①~③の方に業務で従事している方 (家事は除く) | 別居の未婚の子 別居の親族 友人や知人 |
年齢条件は保険期間途中でも変更できる
すでに解説のとおり、年齢条件は若年層に設定すると自動車保険料は高くなります。そこで、覚えておきたいことがあります。
自動車保険は保険期間中に変更があれば、「異動」と呼ばれる手続きで保険内容を変えられる!という点です。
保険期間の途中で、運転者の年齢が変わった場合は変更ができます。
たとえば、同居の子が運転するために両親の自動車保険の年齢条件について、子どもに合わせている方は多いでしょう。就職や進学で別居した場合は、保険期間の途中であってもご両親の年齢に合った年齢条件へ変更しましょう。保険料が安くなる可能性があります。一時払(一括払)なら保険料は返戻される可能性が高く、月払いならその後に支払う保険料が安くなります。
【注意点】
上記のようなケースでは保険料を安くできますが、保険期間の途中で若年層に合わせて年齢条件を低くする場合は、保険料が追加されます。
「保険料が高くなるなら年齢条件を変えたくない」と思うかもしれませんが、設定している年齢条件以下の方が運転時に事故を起こしても補償が得られなくなってしまいます。たとえ自動車保険料が高くなっても正しく年齢条件を設定しましょう。
なぜ若年層(18〜25歳)の自動車保険料は高い?
年齢条件で解説のとおり、自動車保険の保険料は若年層であるほど高くなってしまいます。自動車保険の保険料を決める要素は年齢だけではありませんが、「なぜ若年層は自動車保険が高いのか」と疑問に思っている方も多いでしょう。そこで、この章では若年層の自動車保険料が高い理由を解説します。
若年ドライバーの事故リスクとは
普通自動車の運転免許証は18歳以上になると取得できます。2022年4月1日には民法の改正もあり、18歳は成人年齢になったことから、法的にも18歳は大人とみなされます。
しかし、自動車保険料については、若年層の方がリスクは高いと分析されています。その理由には、「未熟さ」や「前方の不注意」が挙げられます。
①若年層は運転が未熟
若年層は運転経験が乏しく、危険を回避する経験も不足しています。一方の中年期以降は、ヒヤリとする運転経験をした方も多く、危険認識が若年層よりも優れています。そのため、事故リスクが若年層よりも低いため、自動車保険料が安い傾向にあるのです。
②前方不注意の事故が多い
若年層は前方不注意の事故が多いと言われています。居眠りやスマホの操作、友人との会話な度をきっかけに事故に至るケースもあります。警察庁交通局によると、若年層のドライバー(16歳~24歳)は安全運転義務違反になる行為が多く、運転への集中力が欠けている様子もうかがえます。
参考URL:警察庁交通局
平成29年中の交通事故の発生状況
若年層向けの保険料割引はある?
若年層のドライバーは未熟さゆえに事故リスクが高く、保険料が高く設定されています。しかし、重い自動車保険料の負担を減らしたいと感じる方は多いでしょう。
では、若年層向けの保険料の割引はあるのでしょうか。
若年層がターゲットとなっている割引はなく、保険料の節約を検討する場合は、以下の方法で検討しましょう。
加入時に中断証明書がないか探してみよう
自動車保険に新規で加入する場合は、6等級から始まります。(セカンドカー割引がある場合は7等級)。しかし、ご家族の中に中断証明書をお持ちの方がいたら、さらに高い等級で加入できます。
中断証明書とは、お車の廃車などを理由に自動車保険を解約(もしくは満期)した場合に、等級を保存できるしくみです。
中断証明書の有効期限は10年間あり、中断時以外の保険会社での新規加入にも使用できます。中断証明書は、解約した際の記名被保険者本人、その配偶者や同居の家族が使用できるため、若年層の方が自動車保険の新規契約を結ぶ際には、同居している方の中断証明書がないか探してみることがおすすめです。
これから免許返納を迎える高齢者の方は、お孫さんのために中断証明書を発行しておくこともおすすめです。
車両保険についてじっくり検討する
自動車保険は運転者の年齢だけではなく、補償内容によっても保険料は変動します。たとえば、車両保険は自動車保険料の中でも大きな影響を与える部分です。
事故リスクの多い若年層は、本来車両保険にもしっかり加入することがおすすめですが、以下の方法で補償を行いつつ保険料を節約することも検討しましょう。
1.免責を設定する
車両保険は契約者側の自己負担金となる「免責」を設定することができます。免責は一般的に5~10万程度で設定できます。免責を設定すれば、事故時の車両への補償について、保険会社側は負担額を減らせるため、保険料も安く設定しています。
2.購入時の車両は中古車を選ぶ
若年層は事故リスクが高いため、保険料が高いですが、新車を購入してしまうと車両保険も新車に合わせた金額となるため、高額の保険料が発生します。一方で初度登録から月日が経過している車両の場合、時価評価によって補償できる保険金額がそもそも低くなっています。この場合、購入する車両も中古車のため安く、車両保険も安く抑えられます。初心者でまだ運転に不慣れな時期は、中古車を活用することも検討しましょう。
3.ご家族の車を譲り受け、家族が自動車保険の新規契約をする
若年層の方が自動車保険に新規で加入する場合は、自動車保険料がどうしても高いため、家族の自動車保険を譲り受け、譲った側の家族が新たに自動車保険に加入する、という方法も考えられます。
この方法は「吐き出し新規」などの名称で呼ばれています。この手続き方法は以下の通りです。
吐き出し新規の例
親が現在20等級で、子が新規で車両を購入し、自動車保険に加入が必要
↓
親が新規に自動車保険契約をして6等級になり、子が親の20等級を継承する
吐き出し新規は自動車を増車するタイミングで、かつ同居のご家族間であれば可能です。
親がゴールド免許ならさらに新規自動車保険の保険料は安くできます。
等級継承は同居のご家族であれば可能であるため、子が同居していれば吐き出し新規は可能です。しかし、遠方に進学・就職した後だと同居ではなくなるため、吐き出し新規による等級継承はできません。なお、子がすでに新規で自動車保険に契約している場合も、親の自動車保険契約と交換する(親族間で等級を交換する)こともできません。
【等級】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
自動車保険の等級制度とは?保険料の割増引率を徹底解説
補償の重複を防ぎ、保険料を抑えよう
若年層が新規で自動車保険に加入する場合は、主に以下の4つの要素で保険料が高くなります。
- ①免許証の色
- ②契約時の運転者年齢
- ③等級が新規契約のため低い
- ④運転に不慣れのため、補償内容を手厚くする必要がある
自動車保険があまりにも高額の場合、上記の④である「補償内容」を調整することで自動車保険の保険料を調整したくなります。しかし、運転に不慣れな年齢だからこそ、基本補償や特約はできる限り充実させることがおすすめです。
特に若年層は友人を乗せてロングドライブを行うことも多いでしょう。同乗者の補償を用意するためにも、人身傷害保険などもしっかりと加入することがおすすめです。
ただし、補償内容によっては、すでにご家族が加入している補償と重複し、保険料の過払いとなる可能性があります。新規で自動車保険に加入する際は、過払いを防ぐためにも、家族内で自動車保険契約を見せ合い、補償の重複が起きないように工夫することがおすすめです。
中年層(26〜45歳)の自動車保険は安い?
若年層とは異なり、中年層に該当する方の自動車保険は安い傾向があります。では、どうして中年層の自動車保険は安いのでしょうか。
この章では中年層における自動車保険の保険料に注目します。
中年層ドライバーの事故リスクは低い
中年層のドライバーは、若年層と比較すると運転経歴も蓄積していることから、事故率が低い傾向にあります。そのため、セゾン自動車火災保険の「おとなの自動車保険」のように、中年層向けに低保険料・高補償をアピールする保険会社も登場しています。高齢者、若年層と比較すると、注意力はもちろんのこと、気力と体力もあり、事故回避の経験も多い中年層は事故リスクが低いと考えられています。
保険料が低い理由は年齢だけではない
中年層は年齢条件の影響により自動車保険が安い傾向にありますが、保険料が安い理由は年齢だけではありません。中年層で安全に長年運転を続けているドライバーは、ゴールド免許である可能性が高いことも挙げられます。
また、長年安全に運転していると、事故を起こさずに自動車保険の更新を続けているため、現契約の等級が高く、割引率も大きいことも背景に上げられます。さらに保険料を見直したい場合は、見積もりを取得して比較してみると良いでしょう。
【ゴールド免許】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
ゴールド免許と自動車保険の関係性
高齢者層(46歳以上)の自動車保険料は今後どうなる?
近年高齢者ドライバーによる事故が大きな話題となっています。2019年4月に起きた東池袋自動車暴走死傷事故では、高齢者ドライバーによる暴走で母子が亡くなるという痛ましい結果となり、高齢者の免許証返納への世論も一気に拡大しました。
現在この事件では、運転していた加害者側には、控訴をしなかったため刑事事件として禁固刑が確定しています。また、2023年10月には東京地裁の民事裁判にて、1億4000万円に上る賠償命令が民事裁判によって下されています。
最近でも、高齢者による自損事故の映像が多く報道されていることから、高齢者の事故リスクや保険料の今後のゆくえが気になっている方は多いでしょう。
そこで、この章では高齢者の事故に注目し、保険料の今後についても考察します。
高齢者層と若年層はどちらの事故リスクが高い?
近年高齢者による交通事故が大きく報道されていることから、若年層よりも高齢者層の事故リスクの方を心配している方も多いでしょう。
では、実際に高齢者層と若年層では、どちらの事故リスクが高いのでしょうか。
2023年10月に公開された筑波大学による「TUKUBA JOURNAL」によると、交通事故の発生リスクは中年期から高齢に向かって高まっていくものの、若年層と比較すると高齢者の事故リスクの方が低いことが判明しました。
現在日本高齢化社会を突き進んでおり、高齢者ドライバーも比例して増加していますが、事故リスクの点では運転経験の浅い若年層の方がリスクは高く、今後も自動車保険料については若年層が高い傾向が続くと予想されます。
参考URL:筑波大学「TUKUBA JOURNAL」2023.10.23
高齢運転者が事故を起こすリスクは若年者よりも低い
高齢者は自損事故リスクが高い
引き続き、上記の筑波大学の資料によると、高齢者は自損事故によって自らが命を落とすケースが多くなっています。
85歳以上の運転者が起こした事故で、死亡した人のうち、67%が運転者自身であることが分かっています。
自損事故は強制保険である自賠責保険では補償ができない部分であり、高齢者の死傷事故を保険で補償するためには、任意保険が不可欠であることがうかがえます。
事故リスクとしては若年層よりも低いものの、補償の必要性の観点で言うと、今後高齢者層の自動車保険料は上がることも予想されます。
![]()
引用画像URL:筑波大学「TUKUBA JOURNAL」2023.10.23
高齢運転者が事故を起こすリスクは若年者よりも低い プレスリリースより
【任意保険】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
車の任意保険とは?加入するメリットや補償内容、利用例を解説
定期的な運転講習や標識の活用
高齢者となったら免許を返納すべき!という議論が盛んですが、実際には自動車が無ければ暮らしにくい地方都市も多く、容易には返納できないという声も聞こえてきます。
警察庁による2018年の統計結果によると、運転免許証を自主返納したのは、およそ42.1万人(75歳以上が29.3万人)ですが、高齢者人口が増加の一途をたどっている以上、高齢者ドライバーによる事故は増える可能性があります。
免許証の返納は難しい…という方は、以下の3つの対策を検討しましょう。
①高齢者マークをつけること
高齢者向けには、高齢運転者標識(もみじマーク)とも呼ばれている標識があり、現在車両に表示を付けることは「努力義務」となっています。表示の対象者は年齢が70歳以上、高齢者であり反射神経や視力、張力の低下を感じる方が該当します。
努力義務ではあるものの、安全運転を心がけるためには、標識を付けることがおすすめです。
②運転講習の活用
高齢者向けには、現在運転免許証の更新の際に、「高齢者講習」が実施されています。しかし、運転で少し焦る機会が増えた、自宅車庫に擦ってしまったなど、これまで感じなかった不安が少しでも増えてきたら、自主的に運転講習を受けることがおすすめです。
教習所や個人向けの運転講習などもあり、積極的に運転の講習を受ける機会を持つようにしましょう。
③自動車以外の移動方法を活用
JR九州は、2023年10月25日に「運転免許証を返納した65歳以上が対象の、普通・快速列車乗り放題切符」の販売を開始すると公表しました。
福岡・北九州エリアにおける実証実験であり、この取り組みで免許証の返納は加速するかどうかも調査される予定で、1か月5,000円(税込)が予定されています。
こうしたサービスは今後も登場が期待されています
自動車という便利な足を、地域のコミュニティバスや、JRや私鉄などに置き換えて、少しずつ運転の機会を減らしてみることもおすすめです。地方は高齢者のために自治体が主体となっているバスもあり、自動車の代替策としても浸透しつつあります。
参考URL:JR九州
「65歳以上の免許返納者限定のお得な乗り放題きっぷ 「免許返納おでかけきっぷ」の実証実験を行います。」
年齢に合った補償は忘れないように自動車保険を見直そう
運転をする以上は、若年層から高齢者まで、誰であっても交通事故に巻き込まれるリスクがあります。
事故リスクが低いとされる中年層であっても、いつ自分が加害者になるかはわかりません。自動車保険は年齢条件によって保険料は異なり、今後高齢者の増加によって高齢者層の保険料も見直されていく可能性はありますが、保険料を下げるために極端に補償を減らすことはおすすめできません。
適切な補償を用意しておくことで、自賠責保険では補いきれない自損事故や車両の損害もカバーできるほか、加害者となってしまった際の賠償責任もカバーできます。
特に若年層は事故リスクが高いため、万が一に備えてしっかりと補償を用意するようにしましょう。
加入当初はどうしても保険料は高額の傾向がありますが、安全運転を積み重ねることで等級が上がっていき、保険料は安くなっていきます。
まとめ
この記事では、自動車保険について「年齢で変わる」ことに注目しながら、年齢条件のしくみや各年齢層における事故リスクなどを詳しく紹介しました。
自動車保険料を決める要素の1つである年齢ですが、中断証明書の活用や、家族内の等級継承などのテクニックを生かすことで、保険料を抑えつつしっかりと補償を得ることも可能です。
ぜひ本記事を参考に、安全運転を積み重ねながら、自動車保険の契約もじっくりと検討してみてください。